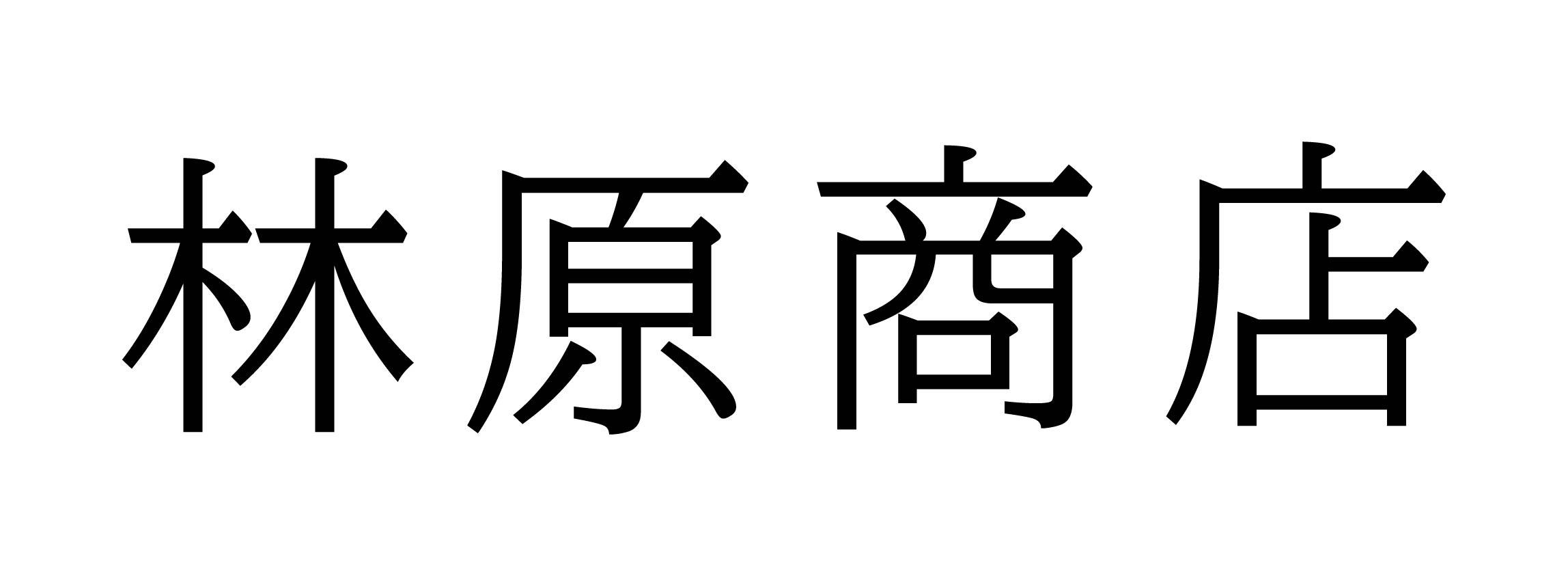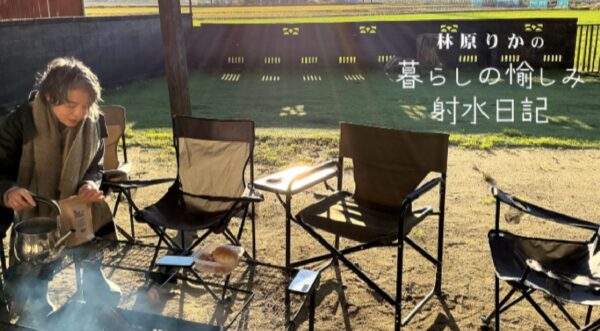大学入試や就職試験の課題としておなじみの小論文。先日、高校生の娘から「小論文って結局なになの?」と質問をうけました。小中学校まで勉強してきた「作文」との違いを説明できますか。
「作文」は「自分」を語り、感性と表現力を評価
小中学校までは、国語で文章を書くとき「作文」とか「感想文」と呼ばれる形態が主です。
この「作文」には、あるテーマがあり、自分の体験やものの見方、感想や感情を表現します。「どう思ったの?」と、いわば「気持ち」を表現します。
たとえば、読書感想文の場合は、本の内容に自分の体験を比較するなどして「自分」の気持ちや変化を語ります。
その過程として、強調したり、感動を高めたり、余韻を残したり、調子をととのえたりするために表現を工夫し、読む人の心に訴えます。
評価のポイントは、感性の豊かさや視点の独自性、表現のうまさ(いきいきとした文章か、表現技法が効果的に使われているか)といったことです。
「小論文」は持論の正しさを客観的に証明。いかに論理的かが勝負
一方、小論文は「説明的文章」というジャンルです。自分の「意見」を客観的な根拠で証明します。「客観的な根拠」とは、事実やデータなどのことです。
そこで、小論文として成り立つには、初めに「問い(課題)」と「自分なりの答え」がありき。
「私は、~と考える。」という意見を述べ、「なぜなら、~だからだ。」という理由(論拠)があり、「例えば~」と事例が続き、「〇〇という意見もあるかもしれないが~」と反論処理し、「これらのことから~」「私の意見は正しい」と結論付けます。
表現技法は必要ありません。それよりも、文意を正確に理解できる文章であることが重視されます。
何より論理的であること、説得力があることが評価のポイントです。
PREP法で小論文の型を身につける
では、「小論文ってどうやって書けばいいの?」と質問されたときのために、覚えやすい組立をひとつご紹介します。
それは、「PREP法」と呼ばれる論法です。
- Point –結論(課題への意見)
- Reason –理由
- Example –具体例(+反論への対応)
- Point –結論(まとめ)
この流れで構成すると、小論文らしく筋道立った文章が書けます。普段の会話やプレゼンなどにも応用できる組立です。
「小論文」の練習はいつでもできる
受験対策などで「小論文の練習はいつから始めるか」といった話題が見受けられます。
文章を書くことの8割がネタ集めや構成づくりであることを考えると、「小論文の練習」はつまり論理的思考の練習といえるでしょう。
と、考えれば、小論文の練習はいつでも、どこでも始められます。
好きなものがなぜ好きなのか、ドラマの登場人物の行動に賛成か反対か、ニュースになっている事柄への是非など、日常の中に「課題」を設定し、その課題への「自分なりの答え」と「客観的な根拠」を説明すればよいのです。
考えたことは、家族で話し合うもよし、SNSやブログで発表するもよし。そうした日々習慣のなかで、自然に養われた力は、とても強力な武器となることでしょう。
これでいいのか自信がない……迷ったときは「言語化コーチング」
自分ではうまく言えない、うまく書けない……そんなときは、林原商店の言語化コーチングがオススメです!
お話を伺いながら、漠然とした想いやうまく言えないお考えを質問で引き出し、整理することからスタート。
ビジョン・ミッション、コンセプトなどを自分らしい言葉にしたり、ビジネスプラン・商品・サービスの企画をお手伝い。
理想に向かうための言葉やコンテンツづくり、オウンドメディア(自社媒体)やSNSの運用についてもアドアイスさせていただきます。
また、コピーライティングや読み物記事、理念と独自性を伝えるHP制作などを、ワンストップでお引き受けすることも可能です。
お申し込みはご連絡フォームからどうぞ! 精一杯サポートさせていただきます!
お仕事のご依頼
メルマガ登録はこちらから
ここだけに掲載している林原りかの「自分史的自己紹介」をお届け後、言葉やブランディングで、ビジネスと人生を充実させるヒントをお伝えしています。返信もOK!